愛知県蟹江町出身の新選組隊士佐野七五三之助を偲び、当町所縁の人物として世に広めようとイベントが行われた。
天保七年(1836年)尾州生まれの佐野七五三之助は正規の尾張藩士であったが、攘夷を志すため脱藩し浪人となった。
文久三年(1863年)に神奈川奉行所支配の横浜外国人居留地警衛隊に身を置くことで、後の高台寺党篠原泰之進、加納鷲雄、服部武雄らと親交を深めた。更にその縁で、佐野の運命を左右する伊藤大蔵(甲子太郎)とも出会うことになる。
同年三月、酔った英国水兵が居留地運上所に乱入する事件が発生。警備担当であった佐野らは、彼らを捕縛し反省させるため拘束したまま海岸に放置した。ところが、英国側が海岸に引き据えたことを抗議する事態となり、奉行所は佐野らを処分することで安易にその場を納めようとした。
切腹を命じられ、自らの大義を遂げる前に果てることだけは避けたかった佐野たちは横浜を脱走した。
息を潜めていた彼らは翌年の元治元年十月、伊藤から新選組に加入するため共に京へ行かないかと持ち掛けられた。その年の六月に池田屋騒動で全国にその名が知れ渡っていた新選組への参加と、逃亡生活を終えることから断る理由は見当たらなかった。(1)
慶応三年六月十四日、新選組が幕臣に取り立てられることに異を唱えた茨木司ら三名と佐野は、会津藩に嘆願書を提出し自らの主張を認めてもらうために詰めていた京都守護職邸にて死亡した。
佐野らの死因については、当時から切腹と新選組による暗殺という二つの説が存在していた。
四人之同志少之内談仕儀御座候間暫時猶豫ヲ顧一間次江立入何之音も無之ニ付島田魁ト申人其間江立入候處四人共見事ニ屠腹致し其上咽頭ヲ鍔元迄突こミ俯伏二而言切致し居候(中略)佐野氏死骸之前ニ安座被致候ニ死骸ムツクト起上我咽ヲ突通居候差添拔取大石江切付(後略)「丁卯雑拾録」小寺玉晁
夕刻二至ル迄待座シタレ共諏訪ノ歸邸ナキニ各殆ント待倦シタル際突然背後ヨリ障子越シ二一聲喚ハルヤ否數本ノ槍ヲ突出シ茨木及ビ佐野富川中村ノ四士ヲ刺通ス不意ナレ共兼ネテ鬪争二慣レタル壮子ナレバ深手二屈セズ忽チ拔合ス佐野重成ハ脇腹ヲ突通サレタル槍ノ柄ヲ振リ片手ニ持タル刀ニテ大石幸次郎ノ面部ヲ瞭口迄切附タリ(後略)「壬生浪士始末記」西村兼文
この事件に関して、現在出版されている研究書の大半が上記のどちらかの記録から推論を導き出したと云える。
「丁卯雑拾録」の編者小寺玉晁は尾張藩お抱えの随筆家で、本書は慶応三年に起きた風俗や風説を収集編纂したものである。尾張藩公認とはいえ、風説をどこまで信じるべきかは記事次第といえよう。
対して、西村兼文は新選組が屯所を移した西本願寺の寺侍である。慶応元年三月に当地へ移転した後、佐野と西村は親交を深めた間柄であったことが著書の中からも伺い知れる。上記の記述に続く文章では、佐野を殺害した新選組と松平容保公への憎悪を滲ませる内容となっている。おそらく、新選組に関する情報元の一人であったのと同時に友人であったのは間違いないだろう。(2)
新選組の研究書のほとんどが上記二説から推論を導き出していると書いたが、その代表的な書と研究者は以下の通りだ。
「丁卯雑拾録」を支持する、すなわち自刃説を取るのは、「新選組日誌」菊池明山村竜也伊藤成郎、「新選組」大石学、「新選組」松浦玲、「新選組銘々伝/佐野七五三之助」前田政記等。
一方、「壬生浪士始末記」を引用し暗殺説を取るのは、「新選組始末記」子母澤寛、「定本新撰組史録」平尾道雄、「新選組誠史」釣洋一、「新選組100話」中村亨、 「新選組全史」中村彰彦、「新選組日記」木村幸比古、「新選組」黒鉄ヒロシ等。(共に敬称略)(3)
著名な研究者たちの間でも意見が分かれているのが実状である。それは、すなわち確証たるだけのものがないからといえよう。いくら新選組でも守護職邸で暗殺はしないだろうという推測に留め、今日の研究に必須ともいえる「新選組日誌」でも、「壬生浪士始末記」には根拠がないという理由で切腹説を取っているくらいだ。(4)
佐野七五三之助ら四人の死因についてはこのまま平行線を辿ったままで良いのだろうか。
ここから先は疑問点を検証した全て推測によるものである。まず、個人的な想像から書いてしまうと、彼らは新選組による暗殺によって命を落としたであろうと考えた。
「丁卯雑拾録」、「壬生浪士始末記」とも瀕死の佐野が大石鍬次郎を斬り付けたとしている。傷の頻度はともかく、守護職邸で監察方が関わっていたことが想像出来る。職分からしても事件を最初から秘密裡に処理しようとした可能性は無くはない。怪我を負った大石が屯所に運び込まれたのなら、全ての隊士が何事かと関心を示したであろう。
(近藤勇は)一先ツ局江引取可申、四人ノ者承知致シ会津公用方ヲ引取ラントスルト使者間*入込ミ四人トモ早ク脇差ヲ抜キ切腹イタス、大石鍬二郎見届ケニ参ルト佐野七五三之進ト申者大石ニ一刀アヒセル(後略)『*原文は門に内』
これは永倉新八の「浪士文久報告記事」の記述だが、幹部の永倉は佐野らの死が切腹であったとしている。だが、この前段には、「其旨趣ハ新選組ニ居ランテハ勤皇不相立、依テ新選組ヲ是非退キ度趣公用方江申述ル(後略)」 、と書いている。
四人が会津藩公用方小野権之丞と諏訪常吉に提出した請願書は、勤皇攘夷実行のため脱藩し新選組に参加してきたが、ここで幕臣の格式を得てしまうことは本国への面目が立たない。自分たちは二君に仕えるわけにはいかないため局を抜けられるよう取り計らって欲しいという内容だ。 永倉が書くように彼らの行動が勤王攘夷の実行が不可能であったからとは書状には書いていない。
これは永倉の単なる記憶違いなのだろうか。局内の動揺を抑えるため、幹部の永倉にさえ事件の真相を知らせなかったということはないのだろうか。「丁卯雑拾録」には島田魁が四人のいた別間に入ったとあるが、彼の残した日記には事件の記述は一切見当たらない。
事件前月の慶応三年五月、将軍徳川慶喜は島津久光、伊達宗城、山内容堂と松平春嶽を四侯会議のために召集した。この時慶喜公は、先年の第二次長州征伐の処理と差し迫っている兵庫開港の問題を打開しようとしていた。だが、将軍の期待とは裏腹に倒幕へ舵を切っていた薩摩の久光公は武家伝奏に大義なき戦だとし長州再征の責任を幕府に求め、毛利藩主父子の名誉を回復すべきと三公との連署で伺書を提出していた。
影響力のある四藩に反意があることを確認した幕府は、佐野たちの事件三日後の六月十七日に二城城で親藩会議を開いた。この時、親藩ではないがすでに幕臣の資格を得ていた近藤勇も会議に出席し、例え徳川に責任があろうと親藩である越前様(春嶽公)が外様に雷同するとは何事か、と強い口調で意見したという。
前年十二月に深い理解をお示しされていた孝明天皇が崩御されてからの一連の世の流れを、会津公と近藤も痛切に感じていたであろう。
自らの公武合体路線を軌道修正することが出来なかった彼らは、これまでと同様に粛清を用いてでも新選組局内からの離脱を許すわけにはいかなかった。と同時に分離した伊藤甲子郎らの行動に対する隊士たちの動揺も最小限に留める必要があったことは云うまでもない。
「二張の弓引かまじともののふの ただ一筋に思ひきる太刀」、佐野が死を覚悟して懐中に忍ばせていた辞世句である。茨木ら三名のものが見つかっていないことから、四人は事前に切腹するつもりは無かったことは明らかだ。
帰隊の説得を拒み続けた佐野たちにすれば、新選組に戻されればどのみち死罪であることは目に見えていた。彼らが突発的に自刃した可能性は大いにある。しかし、当時武力を背景に小藩以上の発言力を持っていた新選組を急遽幕臣に取り立てた幕府の期待を近藤も重々承知していたはずで、故に内からのイデオロギー崩壊を早急にくい止めることの方が重要だったのではないだろうか。佐野らを復隊することが出来ないと判った以上、隊士間に動揺を広げないため、その死を偽装してでも速やかに事件の幕引きをしたいと近藤は考えたであろう。 当然のことながら、会津公も了解していたと考えるのが自然である。彼らの脳裏にはその時、かつて芹沢一派を葬り真相を隠蔽した過去が過ったはずである。
参考にさせていただいたサイト
近代デジタルライブラリー「丁卯雑拾録.第一」
(URL:http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1917609)
(1)共に逃亡した同志の一人大村安宅は上京直前の12月に逮捕され切腹を命じられた。
(2)「壬生浪士始末記」に、慶応元年閏五月膳所城事件に出動した際の佐野の個人的な記述が見て取れる。
(3)「新選組始末記」と「定本新撰組史録」に依る研究者も「壬生浪士始末記」を支持するものとしてまとめた。また、両書とも大石鍬次郎が佐野による刀傷が元で死亡したとしている「壬生浪士始末記」の記述は取り上げていない。「定本新撰組史録」は出典を明らかにしていないが、「新撰組始末記」と内容がほぼ同じであるため一つとした。
(4) 「定本新撰組史録」にも京都西六条の商人和泉屋伝吉の手記として、上記した「丁卯雑拾録」と同一の記述を収録している。和泉屋伝吉が如何なる人物か知り得ないが、市井の商人が聞き得た話ゆえの情報をどこまで信じて良いのだろうか。より新選組、なおかつ高台寺党に近い西村兼文の方が主観は入っているものの信憑性は余程高いと思う。
上記に挙げた著書を読まれた方なら、この記事の推論が「新選組全史」に依存しているのではと考えるであろう。 今回記載した著作の全てにあらためて目を通してみた。大半の著書が事件の直接的な史料からのみ結論を導いた記述に徹している(実際はそうではないと思う)が、当書は事件の背景にある会津藩と近藤勇の思惑に言及している部分が大いに参考になった。
なお補足ではあるが、近藤の甥宮川信吉の書簡にも佐野たちの切腹に関することが書かれている。しかし、上記「浪士文久報告記事」と同じ理由から割愛した。また、明治33年5月3日発行の「史談会速記録 」には、阿部隆明(十郎)の談話に新選組暗殺により四人が死亡したとする証言が掲載されている。佐野らがやむを得ず切腹しようとしたところを槍で突かれたと「壬生浪士始末記」とは異なる証言ではあるが、「新選組日誌」ではそれは取り上げず、茨木司の気質が真面目過ぎたため、近藤に言い含められ進退に行き詰ったのが切腹に至った理由とだけしている。
*この記事は中日新聞2016年2月2日版をもとに書かれたものである
(URL: http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20160202/CK2016020202000055.html)
*記事の転載は厳禁とします
*関連記事検索はタグ新選組隊士列伝
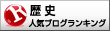
心に感ずるものがありましたら、応援お願いします